視線が絡む一瞬前に目を逸らせば、それを4回繰り返していることに気がついた。
あれから一週間。…一週間、経ってしまったのだ。
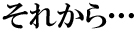
「今日の練習試合は3ON3で行う。」
引退後、受験勉強に専念するという名目で頑なに体育館を訪れなかった元主将赤木の声は、相変わらず重厚的で、それでいてどこか弾んでいた。
誰よりもバスケを愛していた彼が勉学のためにそれを禁じて早数ヶ月。耐え切れずにここを訪れたのは先週のことで、来たら来たで誰よりも楽しげに部員を扱くのだから、さっさと来てればよかったのに、と一同は言わずにはいられなくなっていた。
「あらまぁ、楽しそうな顔しちゃって」
「ほんと!お兄ちゃんたら、わたしが部活の話しようとすると勉強に差し支えるとか言って取り合ってもくれなかったのに」
彩子と晴子が小さく笑いあって赤木を盗み見る。それから、ハッと気付いて花道を警戒した。
こんな、いかにも楽しくてたまらないといった顔で練習内容を話す赤木を前に、あの花道が黙っているわけがない。慌ててハリセン片手に臨戦態勢を取る彩子に、しかし肝心の彼は大人しく、ともすれば暗く沈んでいるようにも見えた。
「…?おかしいわね」
小首を傾げる彩子に、晴子も同意だったらしい。曖昧に微笑んで、でも何もなければそれにこしたことはないですよね、と彩子を促した。
いつもならいの一番に「さっさと帰れゴリ!」くらい言ってのける彼は今、実は、それどころではなく狼狽していたのだった。
ハーフパンツに両手を突っ込み、所在無く視線を巡らせる。花道が本当にどうしていいかわからない時にする仕種をここでしてしまうには、それなりの理由があった。
だって、と花道は誰にするでもなく言い訳めいた事を思った。
野郎が、いつもと全然変わんねー顔してやがるから。…だからだ。こんなに調子が悪いのは。
眉間に皺を寄せ、花道は俯く。赤木の声も笛の音も、どうしてだろう、どこか遠いところの出来事のように響いていた。
一週間前、花道は流川に突然キスされた。続けてすきだ、と言われた。それから花道が「嫌じゃない」といって同意の上で交わしたキスを後に、流川は飛躍的に花道に接触するようになった。
それは、居残り掃除を言いつけられた体育館でだったり、人気のない部室でだったり、大抵は誰もいない時を見計らっての接触だったが、それが花道の日常を変えてしまう程の威力を持っていたなんて、花道自身予想もしないことだったのだ。
接触なんて、たかがキスひとつである。二人きりになった途端に醸し出される流川のなんともいえない空気が、花道を硬直させ身動き不可能にさせ、仕舞いにはいいようにキスさせてしまうのだ。
じっと見つめられて、言葉少なに呼ばれて。いちいち応じる自分も大概馬鹿だとは思うけれど、真っ黒な瞳をゆるやかに細められると何も考えられなくなるのだから仕方ない。
その上、唇と唇の触れ合いはびっくりするくらい心地良くて、苦しくなる程緊張するのに、ずっと触れていたいような気にもなってしまうのだから対処に困るのだ。
そんなことを連日続けられて、一週間だ。
今まで人とこんな風に接触を続けた事などないのだから当たり前かもしれないが、花道の頭の中は最早、制御不能なまでに流川で敷き詰められている。
困ったのは、そんな思考が日常生活の中でも容赦なく花道を襲って、それはもう、授業中だろうが部活中だろうがお構いなく花道を埋め尽くしてくる事だった。
あの目で、どあほうと呼ばれる。甘やかな仕種で頬を撫でられる。それを何でもない時でさえうっかり思い出してしまい、流川が近付く気配だけで、どうしようもない動悸が身体全体に響いて、自分でも情けないとは思うけれど勝手に全身赤くなってしまう。
そんなのがまた今、部活中だというのにまるで条件反射のように出てしまっているのがわかるから、本当に心底困るのだ。
赤木をはじめ、木暮や桜木軍団まで集まった今日の体育館はいつも以上に賑やかなのに、それすら自分とは別次元のところにあるようで花道はため息を漏らした。
…大体、なんでこいつは普通でいられるんだよ。
ちらりと流川を見遣って睨む。やはり今日もいつも通り無表情だ。
自分ばかりがこんな調子で割に合わないと思うのは、当然じゃないだろうか。
花道を取り巻く景色は日常のそれで、今日は元主将赤木を加えて部員達も心なしか浮き足立っている。それは、もう終わってしまった夏を彷彿とさせる光景でもあった。
赤木は勉強で凝り固まった肩を解すように腕を回し、その横で木暮は屈伸をする。どうやらこの男も鬱憤が溜まっていたらしい。眼鏡の奥で隠しきれない笑みが瞬いているのを確認して、赤木は口元を引き上げた。
やはりここはいい。教室にいても自宅にいても、疼く体が求めるのは最終的にはここだ。ここにいる間だけは、何も考えずにバスケができるのだ。
久方ぶりに聞くシューズの擦れる音やボールの感触に思わず頬が緩むけれど、しかし赤木は同時に奇妙な違和感を感じていた。
いつもと違う。いつも通りの体育館なのに、なにかが違う。
その正体をすぐに見つけてしまって、赤木はピクリと片眉を吊り上げた。
「桜木!聞いとるのか!?」
違うものの正体―桜木花道に容赦のない怒号が飛ぶ。
明らかに上の空だった花道は赤木を見たが、その顔は未だどこかに意識をとられているようだった。
赤木は小さく息をつき、花道を見下ろす。
「桜木、今日はやけに大人しいな。部がよくまとまっている。」
いつもこうなら皆が集中できていいんだがな、と嫌味をこめて赤木は続けたが、それでも異様に大人しく反抗してこない花道に調子が狂ったのか、先を噤んでしまった。
「…おい花道、へーきかよ?」
聡く気づいた宮城が肘で花道の腕をつつき、耳打ちする。なるべく刺激しないようにニヤリと笑みまでみせてやったのに、当の花道といえば「あ?あー…、あぁ。よゆー。」等となんとも覚束ない返答である。
それに返したのは、流川だった。
「よゆーな訳ねーだろ、どあほう。」
すると今までぼんやりとしていた花道の目に、さっと火が灯った。
「あぁ?!てめ…なんだと?!」
「せつめー、ちゃんと聞いてたのかよ?」
「き…聞いてたに決まってんだろ!」
「ふーん。じゃあ、てめーは誰と同じチームだ?」
「ぬ…」
ホラな、といわんばかりに流川は鼻で笑った。その姿にムッカー!と鼻息を荒げるのは花道で、落ち着けよ花道!と止めに入るのは宮城だ。ダンナのゲンコツが飛ぶぜ?と、なんとかその場を収める。
面白そうな気配にわくわくと身を乗り出した無責任軍団…改め桜木軍団は、呆れ顔の水戸洋平に諌められて不満顔だったが、どうにか再開した部の練習にいつしか霧散していった。
そうして、今だ。
「ふぬー!なんでオレにパス出さねーんだ」
「てめーに出したら点決まんねー」
「んだとコラ!」
すっかり夜に包まれた体育館に残るのは、花道と流川の二人である。
最後の最後まで赤木にもう帰れと言われ続けていた花道だったが、こんな時だからこそ帰りたくなかった。帰るわけにはいかなかった。
ボールを掴んだまま、キッ、と流川を睨む。こいつに、この男に、バスケまで侵されてたまるか。
自分の不甲斐なさにめげそうになりながらも、花道は思った。
今日一日で、何度流川を思い出してしまっただろう。その目を、感触を、声を。
近付かれれば身体は硬直し、鼓動は馬鹿みたいに早くなる。顔どころかきっと全身真っ赤だろうし、そんな状態でシュートやリバウンドが決まるわけもなかった。
情けなさにじわりと涙まで浮いてきて、花道はもう、本当に自分が嫌になってきた。
「…どあほうが」
必死の形相で流川と対峙する花道に、流川は深く息を吐いた。いつも通りのその仕種が、情けない自分との差を思い知らされた気がして、花道はぎゅっと唇を噛んだ。
なんで、自分ばっかり。
悔しさに目の前が赤く染まる。
そんな花道をどう捉えたのか、流川はひらりと身を翻して床に散らばったボールを拾い集めていく。
「もー今日は終わりだ」
片付ける、と続けて花道に向き直る彼は、花道の手にしていたボールをひょいと奪うと籠へ放り投げた。
きれいな放物線を描いて収まるボールを目で追いながら、花道は呆然と呟いた。
「なに、勝手に決めてんだよ…」
「…?」
「帰るならてめー一人で帰れよ。俺は残る」
「どあほう、いい加減にしろ。もー警備員も帰る時間だ」
「うるせえ!ほっとけよ!さっさと帰れ!」
「…何、意地張ってんだ」
冷静に返されて、花道は益々激昂した。自分でもどうしてここまで意地を張るのかわからない。けれど、流川に振り回された挙句、言いなりになるのは死んでも嫌だった。
「意地なんか張ってねーよ!もーいいから早くどっか行、っ」
続くはずだった罵声を流川の手のひらで遮られて花道は目を剥いた。急激に詰められた距離と、流川の視線が花道を射抜く。
「落ち着け、…どあほう」
瞬間、早まる鼓動。上昇する体温。…ああ、まただ。またこの症状だ。
泣きたい気持ちで花道は流川を睨んで、流川はゆっくりと手を離した。代わりに顔が近づいてくる。
「…っ、」
重なった唇から暖かさと湿った柔らかさが伝わってきて、頭がくらくらした。
キス。キス、されている。何度目かなんてもうわからない。ただ、唇を割って入ってきた塊が花道の舌を丹念に擦り上げるのがたまらなくて、こういうのは何も考えられなくなるから嫌だって前に言ったはずなのにと花道は目を瞑った。
くちゅ、ちゅ、という粘膜の絡む音は、常の体育館では聞こえる事のないものだ。それが更に花道の羞恥と発熱を煽る。立っていられなくてかくんと膝を折ると、流川は器用に花道をしゃがみ込ませた。
何も考えられない。でも、何か考えなければいけない。
熱を注ぎ込まれるみたいな濃厚なそれの合間に、花道はこのままじゃ駄目だとなけなしの理性で覚りながら、意味のわからない熱に喘いだ。
「っ、…は、」
顎に添えられた流川の指が頬を伝って耳朶を擽る。ぞくりと背を走ったものに勝手に涙が溢れてきて、こんな風になるのはやっぱり自分だけだと確信した途端、涙腺が崩壊した。
「も…、やめろ、っ」
ひくりと喉を鳴らして発した声は流川の動きを止めた。唇を解かれて驚愕の眼差しで見据えらる。
「何、泣いてんだ」
「…こんなん、俺じゃねえ」
「あ…?」
「俺ばっか、こんなん、っ、もう嫌だ」
悲痛な思いを吐き出すように、しゃくりあげながら花道は立てた膝に顔を埋めた。
流川の前でこんな情けない姿ばかり晒してしまう自分が嫌で仕方ない。
何でこんな事になったのだろう。花道は一週間前を思い出してちいさく肩を震わせた。
あの時、流川に違うことを言っていたら、今こんな事にはならなかったのかもしれない。
そこまで考えて、不意に流川が何か呟いたのが聞こえた気がした。それがあまりにちいさくて聞き取れなかったので、花道は涙でぐちゃぐちゃの顔をどうするべきか少し悩んだ後、恐る恐る顔を上げ、…そして唖然とした。
滲んだ視界に映ったのは、体育館の無機質な蛍光灯だけ。他にはもう何もない。
そこに放置されていたボール籠を残して、流川はいつの間にかいなくなっていたのだった。
何で急にいなくなったのかとか。あの時何を言ったのかとか。
明け方まで花道を悩ませて消えなかった理由が漸くわかったのは、翌日の部活時だった。
朝練のときからおかしいとは思っていた。だけど、ここまで徹底的にされると流石に花道も理解せざるを得なくなった。
流川は、花道を無視している。
それはもう、わかりやすく完璧にだ。
集合の合図から今現在の紅白戦に至るまで、一度たりとも視線は合わせないし、花道が三井や宮城と騒いで馬鹿をしていても何のアクションも取らないのだ。流川は元々無口なだけに、そうなるととことん無言で不気味である。
早々に気付いた彩子が花道に何かあったのかと尋ねてきたけれど、まさかこういう手段に出られるとは思っていなかったのだ。花道は知らないと告げるだけで精一杯だった。
なんで。なんでなんで。花道は沸々と湧き上がる怒りを腹にためてボールを放った。
全国以来、精度を上げたはずのフリースローは本日3本目で、それを今、見事に外した。チ、と舌打ちしつつ、もう一度構えてゴールを見据える花道は、ボールを放とうとして取りやめた。
ボールはそのまま宮城に繋ぎ、宮城は見惚れるほどのカットインで内側からゴールを決めた。さすが神奈川屈指のガードといったところである。
しかし敵チームの安田が拾った次のボールは、流川のドリブルで瞬く間にゴール下まで迫ってきた。
「花道ー!抑えろー!!」
「ぬ…お、おう!!」
猛進する流川を前に、一瞬だけ隙ができてしまった。花道は跳ぶタイミングを見誤り、その結果ゴールに飛び込んできた流川と縺れ合って床に叩きつけられた。
落ちる直前、受け止めるように流川が下になった気がしたのは確かだったようで、気が付いた時には流川は花道の下敷きになって倒れていた。
呆然とする花道に、アンタがぶつかったんだからアンタが連れていきなさい、と彩子は保健室の付き添いを花道に命じ、運悪く外出中だった保険医を待って今に至る。
「…くそっ」
ベッドに横たえた流川を見つめて花道は眉間に皺を寄せた。
さっきまで散々無視してたのに。なんでこういうときだけ。
怒りと疑問と、それから少しの歓喜が花道を襲う。花道の身体は相変わらずあの症状を起こしてるし、未だに落ち着かないというのに、頬だけが勝手に緩み出して収集がつかない。
眠ったままの流川は心配だが、彩子の診断では軽い脳震盪だろうということだし、そう簡単にどうにかなるようなタマじゃないと花道は思っている。
それはいいとして。さしあたっての問題は、流川が保険医が来るより前に目覚めたときの対処だ。
今日一日無視してくれた礼と、昨日突然消えた事。どちらを先に問い詰めるべきか。
それより、昨日あんなに泣きじゃくった事への弁解もしなければいけないだろう。
あれはちょっと気が動転してただけだと。別にお前のせいで泣いたわけじゃないと。そもそも、この天才ともあろう者が流川相手に泣くわけがないということもきちんと伝えなくてはならない。
そうは思うが、流川をみているだけでも頭の中はふわふわしているし、何だか泣きたい気持ちになってしまっているのが悔しい。現に、流川が小さく身じろぎしただけで心臓が狂ったように悲鳴を上げる始末だ。
ああもう、ほんとに。何なんだこれは。
流川の一挙手一投足に一々反応しているのが馬鹿みたいだと思う。
とにかくこんなことで悶々とするのが腑に落ちなくて、花道は何か気が紛れるものはないかと窓の外に目をやった。
紺碧とコバルトブルー。それから藍の混じった空にイチョウの葉がくるくると舞っている。
まるで自分のようだと自嘲しながら、外に出たら少し冷えるかもしれないと思った。
秋風に漂い続ける黄色をぼんやりと眺めて、今夜は秋刀魚にするかなと思考を廻らせたところでベッドが軋む。
花道は慌てて現実に向き直った。
「ル、カワ」
起き上がった流川は未だどこかぼうっとしていたが、花道を視界に捉えるとゆるく目を細めて、どあほうと呼んできた。
だめ。無理。ずるい。
そう思ったのと、花道の身体が反応したのは殆ど同時だった。
全身を駆け巡る熱い血に動揺しながら、花道は必死に平常を装う。
「お、おまえ、大丈夫なのか?」
「平気」
「そ、そうか。あー、っと、あれだ、先生まだ来てねえみたいだからもうちょい待ってろな」
「ワカッタ」
「おう、…あ、じゃあ俺、彩子さんに報告、」
「どあほう」
ここにいろ、と手を取られてびくりとした。顔が熱くなった気がする。
「おい、ちょ、」
離せと言う前に身体を引き寄せられて驚いた。流川の腕が背中に回り、腰のあたりまでゆっくりと撫ぜてくる。
「どあほう、怪我は…?」
「け、…あ?」
「痛くねー?」
「い、ああ、俺は何ともねーよ、天才だし…!」
「ヨカッタ」
なんだ、…これ。さっきまで完全無視してたヤツが急になんだこれ。
花道は盛大に狼狽えて顔を逸らした。
これ以上流川に見られていたら、触れていたら、きっとどうにかなってしまう。
ぎくしゃくと腕を伸ばして花道は流川の肩を押した。不自然に距離を取るのは、自分がこれ以上情けない事にならないためだ。
しかし流川はそれは否と取ったらしい。明らかに不機嫌顔になって花道を睨む。
「…何で避ける?」
「別に…」
「…今だけじゃねー、あんときからずっとだ」
その言葉に花道は顔を上げた。
知ってる?気付いてる?…この正体不明の症状に。
そう思った途端、花道は急激に逃げ出したくなった。だって、こんな恥ずかしい事はない。
自分の気持ちが駄々漏れしている様を言い当てられたのだ。じっとなんかしていられなかった。
けれど流川はいやに真剣な顔で言葉を紡ぐから、その音程に雁字搦めにされて花道は動けない。
「近付くのも触るのも嫌ならって、シカトしてみた。…そしたら、どあほうから近付いてくると思ったから」
でも、と言葉を切って流川は花道を射抜く。圧倒的な熱線。それから言葉。
「…嫌なら、好きじゃねーんなら…もういい。もう、しねー。」
視線だけで焼かれそうだと思った。言葉の意味は理解できなかった。だけど今、確かに流川は音を立てて花道を貫いた。
無防備な身体のど真ん中が、鋭い刀でも突き刺したようにきんと冷えてゆく。その部分から抉られた内臓が赤々と爛れて流れ出ていくようだ。
「っ、ルカワ、」
ひゅ、と息を吸ってどうにか吐き出した名前は、流川には届かずにドアにぶつかって消える。
そこでやっと彼が出ていってしまったことに気がついた。
「…なん、だよ」
花道は呆然と呟いた。
何が何だかわからない。それなのに、自分でもびっくりするくらい身体が冷え切っている。どうしてだろう。
悴んだ指先を握り締めて花道は目を瞑る。
流川は今、なんて言った。なんて言って、出ていった。
数秒前の事を数十回思い返してみて、だけどやっぱりよくわからなくて立ち竦んだ。
ドアを開けば流川がいるのに、もう一度呼べば聞こえる距離なのに。ここから飛び出して捕まえて何言ってやがると凄んで喚いて。…できるわけがない。
コツコツ、と廊下に反響する足音が例えようのない不安を引き寄せて、やがて消えた。
その静寂に身を浸して花道は絶望的に覚る。
あれは、流川の最後通告だったかもしれない。
next 2